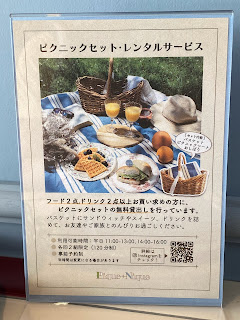先月、映画「月」の公開初日にあわせてヴィヴィアン佐藤さんのトークショーが行われました。
この映画、観てみたい気持ちと
でも観たら落ち込んでしまいそうでこわいなぁという思いがありましたが
ヴィヴィアン佐藤さんのトークショーもあるということだったので、都合をつけて行ってきました。
でも実際観てみて、そんなに思ったほど落ち込まなくてよかった、というのが正直なところ。
それから上映後のヴィヴィアン佐藤さんの解説が聞けたのがやっぱりよかった!!
ヴィヴィアン佐藤さんからは映画の見方を教えてもらった、という感じかな。
映像に映っていること、それだけが全てではない。それだけが真実ではない。
迫真の演技であればある程、真実味を帯びている。
映画に出てくる登場人物は映画を観ている人一人ひとり、誰にもなりえる、鏡像になっている。
どう自分の言葉で考えていけるか、(映画を)その材料にして欲しい。
上映時間の2時間半はあっというまでした。
映画を観ながら、いろんなことを思い出したり考えたり。
例えば『コスパ・タイパ』という言葉が思い浮かんで
やっぱり自分もそういうことついつい考えてしまうのだけれど
そういう社会的な風潮がモンスターを生み出してしまったのかな、とか。
それから『心はどこにある?』ということ。
人間の“心”ってどこにあるんだろう?胸?頭?脳みそ?
博士が自分とそっくりのロボットをつくるのだけれど
みんなはそのロボットの方が博士よりも博士らしいっていう
その人らしさって一体なんなんだろう?
本人よりもロボットの方が本人らしいって本末転倒みたいな
(でもなんとなくその理由も分かるような気がしたり)そんなことを思い出したり。
たとえ話ができなくても心はちゃんと存在するし
心の中にあることを表現する、言語化するって実は高度なことなのかもしれないな、って思ったり。
言葉が出てこない子だっているし、言葉が出てこないから心がないわけではないのに、って。
「人」の定義や「生きる意味」って何だろう?
生産性がないと生きている価値がないのだろうか。
私は映画の中の“彼”が思っている正義を、ひっくり返せるような言葉が思いつかない……。
それからこういった施設では、本当にこんなこと(虐待)が行われているのだろうか
以前、八王子だったか、精神病棟のことが問題になったし
福祉の研修では、自分がストレスフリーでないと弱い人を虐待してしまうから
自分自身の心に余裕があることがとても大切だと教えられる……。
映画を観ている分には、スクリーンに映し出されているものは本物に似せたつくりものであり
例えば血だって本当の血ではなく“血のり”だと思うから
どこか安心してスクリーンを見られるのであって、あれが全て本物だったらとうてい直視できない。
(でも実際に起きたことを忠実に再現しているということなので
ラストシーンで事件につきあわされる羽目になったあの人は、あんな現場を見せられてしまったら
もう普通の意識を保つことはできなくなってしまうのではないだろうか、と思ったり)
映画の中ではいろんなテーマが混在していて
出生前診断をするかしないか、そんな内容にも触れられていて。
私は下の子ちゃんがお腹にいたとき
上の子ちゃんと真ん中ちゃんが水ぼうそうになったことを思い出しました。
私も水ぼうそうにはかかったことはなくて
子どもたちが小児科の先生に診てもらった時にそのことを話したら
「かかりつけの(産科の)先生に相談してください」と緊迫した面持ちで言われて。
で、そのあとちょうど診察があったので産科の先生に相談したら
「もしお母さんも水ぼうそうになってしまったら、お腹の赤ちゃんおろしますか?」と聞くので
「産みます」と即答したら
「じゃあ、心配しなくたっていいじゃない」と先生は笑って、あー、この先生、好きだなぁって。
真ん中ちゃんが逆子になってなかなか元の位置の戻らなかったときも
「江戸時代だって逆子はいたんだよ。でもみんなちゃんと自然分娩で産んでたんだから大丈夫」
って。
(でもそのあと、ぎりぎりのタイミングで元に戻ってくれたけど)
上映終了後のヴィヴィアン佐藤さんのトークと、一緒に上映を観た方が感想を発表していて
あくまでも物語であって、それが全てではない、というヴィヴィアン佐藤さんの言葉から
考える事自体、めんどくさい。考えることを他人にゆだねてしまっている。
社会全体がそんな流れになってしまっているけれど
この映画は物語であって、それがすべてではない。そこから考えることが大事。
という言葉が心に残りました。
確かに、私も考えることがめんどくさいと思って他人に考えをゆだねているかも。
そしてある施設の管理者。
映画に出てくる“彼”は
境界知能(簡単にいえばグレーゾーンといえばいいのかな)だった。
今、自分がお預かりしている子の中にも
将来、彼のようになってしまうかもしれない子が出るかもしれない
そう思って言葉を震わせていたその姿もまた、印象に残りました。
誰の心の中にもある、差別という気持ちだったり、正義だったり
映画のなかに出てきたきいちゃんを思ったり、主人公が自問自答するシーンだったり
会場で一緒に映画を観た人たちがそれぞれに、静かに心の中で
いろんな考え、思いを反芻していました。
こうやって映画を観た後に解説を聞いたり、感想を共有することで
映画が自分の心の上を素通りすることなく、心の中にとどまる。
沢山の小石が心の中に放り込まれて、さまざまな波紋が生まれるように
心の中の川に大きな杭が打ちこまれて、そこにまたいろんなものがひっかかるように。